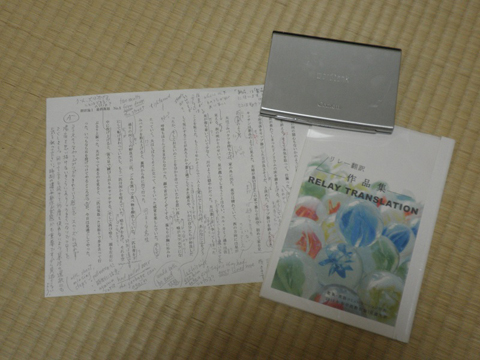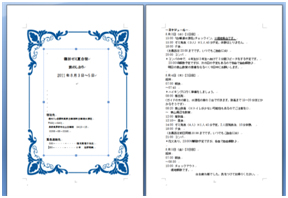3年生にもなると、さらに専門的な学びへと展開していきます。そして、講義で聞いて学ぶ段階から、自分たちで考えて試みる段階へと移ります。
心理学で扱われるさまざまな心理現象のうち、知覚や認知にかかわる問題について自分たちで実験を試みながら考えていきます。例えば、物理的な長さは変らないのに、ある条件を加えるだけでより長く見えたり、短く見えたりします。見え方が変れば、当然振る舞い方も変ってきます。では、そのある条件がなぜ見え方を変えるのか、理由を考えながら、さらに実験を計画していきます。
授業ゼミ紹介ブログ
恵泉地域言語活動研究会での学び 英語コミュニケーション学科
2011年09月22日
投稿者:才丸 光
ゼミ/授業名:英語教育特講II、IV
私はゼミでは語用論やコミュニケーション理論を勉強していますが、教職課程を履修していることもあり、教育や地域との交流を図るボランティアにも積極的に参加しています。
学内のボランティア団体としては「恵泉地域言語活動研究会」に所属していて、月に1度小学校に行って担任の先生と一緒に英語の授業を行う活動や、詩や昔話などを暗記して地域の社会福祉施設などに語りに行く活動を主に行っています。それぞれ前者の活動はKEES、後者の活動は恵話会という個々の組織として動いていますが、「恵泉地域言語活動研究会」に所属する多くの学生は両方の組織を掛け持ちしており、それぞれ使う言語は違えども、その根幹にある「言葉の魅力を通して様々な人と交流を深める」という姿勢は同じだと考えています。
実験を通じて心理学を学ぶ 人間環境学科
2011年09月20日
投稿者:喜田安哲
ゼミ/授業名:喜田ゼミ
「プーさん」は曲者!? 英語コミュニケーション学科
2011年09月10日
投稿者:小島 佐喜子
ゼミ/授業名:翻訳論I
「翻訳論I」の授業紹介
翻訳論Iのクラスでは、最初の数回で「翻訳とはなにか」や、「翻訳不可能な英語」などといった理論を学んだあと、実際に翻訳をしてみるという実習形式に移ります。
授業では作品をいくつかにパート分けし、1パートごとに二人の学生が翻訳を担当します。それぞれが家で日本語に直し、先生がそれを「たたき台」にして授業で他の学生と一緒に、英文の中に隠された落とし穴について考えていきます。私たちは、先生が訳に修正を加えたものを返却していただけるので、それを参考に読みやすくきちんと原文が表現されているかを考慮し、何度か修正をして提出します。学期の終わりには先生が、クラス全員の訳をまとめ、「リレー翻訳」という冊子を作成してくださります。
ニホンジカとニッコウキスゲ 人間環境学科
2011年09月05日
投稿者:篠田 真理子
ゼミ/授業名:篠田ゼミ
2011年8月、篠田ゼミ恒例、2泊3日の夏合宿を行ないました。今年は白樺湖畔に宿泊。宿の手配、しおり(図1)、会計、時間管理と、全て4年生が役割分担して運営しました。
2日目には、これも恒例の自然観察ハイキング。地元の山に詳しい方に案内をお願いし、霧が峰高原散策を行いました。車山山頂で思いもよらず気象庁のレーダー基地を見学したり、湿原の植物を満喫したり、半日の充実したコースでした。
ちょうどニッコウキスゲ(図2)が見ごろでしたが、数年前はニホンジカの食害にあって、ほとんど花が咲かないときもあったそうです。そのため電気柵(図3)が設けられ、今年は無事に開花を迎えました。柵の内と外では一目見て花の数が違います。そこから、美しい高山植物を眺めるだけではない疑問がゼミ生からあがってきました。
園芸療法の授業について 人間環境学科
2011年08月22日
投稿者:澤田 みどり
ゼミ/授業名:澤田ゼミ(園芸療法)
園芸療法とは、植物や植物が育つ環境を、人の心や身体のリハビリテーションに活用する方法で、支援を必要としている高齢者の心身機能の維持向上や、介護予防や認知症予防、生きがいづくりとして注目されています。知的障がいや身体障がいをもつ方、心の病いとともにある方の日常生活支援や就労支援、薬やアルコールに依存している方への自立支援、ひきこもりや不登校の青年たちへの社会参加支援、病院、施設、ホスピス、コミュニテイ―と活動は広がっています。